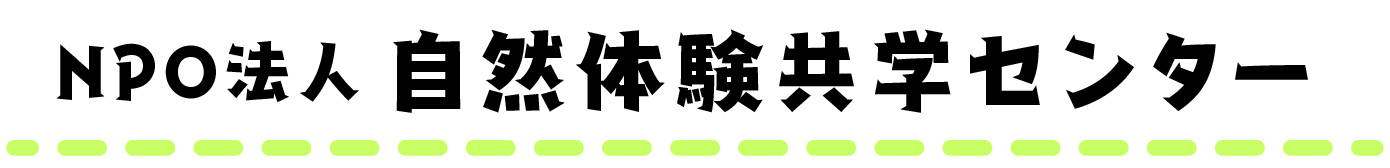きゅうり(一)
むかし、むかし、ぎょんどさんの神様である(すきのうのみこと)様が戦いをなさった。その時、神当部(かんとべ)村では、棚にはわすうまぁいきゅうりを作っていたが、他の部落では、地にはわすきゅうりだった。
そのため、牛に乗って戦いをされていた尊様や味方の武士たちは、きゅうりのつるにひっかかり転んだりして、非常に苦しみ、戦いに負けた。その尊様は、村人に「今後、きゅうりを絶対に作ることはならない」と御触れを出した。
その後、今だに神当部集落では、きゅうりを作る人がいないと言う。たまに、二、三軒の家で作るが棚でなく、地にはわすきゅうりを作る程度で、ほとんどの家の人は買ってきたり、他の集落からもらったりしている。
きゅうり(二)
昔、大野に、大変わがままな殿さんが、おったんじゃと。城にいるのにあきあきして、家来を呼んで、 「わしは、これから狩に出かける馬を持てえ。」 と家来に言ったんじゃ。そのころ、村はちょうど収穫前のだいじな時であった。そこで、この家来は、 「殿、今ゆかれたのでは何も捕れませんので、もう少し後にされてはいかがですか。」 というたんじゃが、いったん言いだしたら聞こうはずのない殿様は、家来を数人従えて味見の村にやって来て、野と言わず、畑と言わず所かまわず荒しまわり、畑の作物を傷めるばかりで獣はおろか、鳥さえも一つも収穫がなかった。狩にあきあきしたところちょうど神当部にさしかかった。そのとき運悪くうさぎが一羽殿様の前を横切った。殿様は、これを見逃すわけはなかった。
「それ行くぞ。」と、殿様は、先を取って畑につっこんだ。
ちょうど畑には、きゅうり棚が作ってあり、きゅうりがいっぱいなっていた。うさぎは、殿様が追いかけて来ると見るなりきゅうり棚の下に逃げこんでしまった。それを見た殿様は、馬できゅうり棚を飛び越えようとしたのだが、馬がきゅうりのつるに足を捕られ、殿様は、馬からほうり出されもんどりを打って、したたかに腰を打ってしまった。
べつにきゅうりが悪いわけでもないのに、さもそこに、きゅうりがあることじたいが悪いかのごとく、 「以後、この村では、きゅうりを作る事あいならぬ」と怒り、立て札を立て、きゅうりを作ることを禁じた。これを破った者は、きびしく罰せられた。
以後、神当部では、きゅうりは作られなかった。
ぎよんどぎつね
昔、昔、神当部のぎょんどさんには、大きな古ぎつねがいて、そこを通る村人を、騙したり、そこらの畑を荒らしては、いたずらばかりしていたんやと。
ある日、彦太郎という子が、おっ母さんの使いで、中手まで油揚を買いに行ったんやと。店の人は、その油揚を、ふきのはっぱにつつんで、それをわらすべでむすんでくれたんや。彦太郎はそれをぶらさげて帰ったんやと。
帰る途中、ぎよんどさんの所で、のどがかわいたんで、水を飲んで、ちょっと一服していたら、うとうとしてしもうて、眠りこけてしもたんや。それを待っていたらしく、ぎよんどさんのお堂の後から、きつねが、ひょこんと出て来て、彦太郎が持っていた油揚を取り上げてみんな食べてしまったんや。それから、油揚の代わりに、牛のふんを、ふきのはっぱにつつんで、元どおりにしておいたんや。 そうとは知らん彦太郎は、あたりが薄暗ろうなっているので、その牛のふんをぶら下げてあわてて帰ったんや。
「われ、なにしに中手まで行って来たんや、そんなに牛のくそが好きなら、今夜から馬屋へ行って、牛と一緒に寝れ。」 って、おっ母さんに、なぐられるやら、けられるやら、こっぴどく怒られたもんだから彦太郎は、もうくやしくて、どうしようもならなんだんや。
あくる日、ぎょんどさんの所を歩いていたら、中手の方から、見たことのある富山の薬売りのおんさんが、歩いて来るんやと。その薬売りがぎょんどさんの前まで来ると、何思うたんか、くるっと回って中手の方へ行くもんや。初めは、何か忘れ物でもしたんかなあと思っていたら、またしばらく行くとくるっと回って来るんや。それが、何辺でもやっているさかいに、 「あの薬売りのおんさんは、きっと、きつねに騙されているにちがいない。きのうは、ひどい目におうたさかい、今日は、うらがつかまえて、ひどい目に合わせてやるわい。」 と、彦太郎は、そっとお堂の後の方に回わって見ると、案の定きつねが、うれしそうに、しっぽを「ペーン」「ペーン」と動かしているんやと。
「ペーン」「ペーン」としっぽを動かす度に、薬売りのおんさんは、くるっ、くるっと回わるんやと。きつねばかりか、彦太郎もおかしくなって今にも声を出して笑う程やったんや。
「中手から、神当部までは、何んと遠いんやろ、いくら歩いても家一軒も見えて来ん。」 と、薬売りのおんさんが、ぶつぶつ言うて歩いているさかいに、きつねはなおいっそううれしがって、しっぽを動かすのに夢中になっているんや。だから、後から彦太郎が近づいてくるのを、全然気がつかなんだで、一間程近くにそっと近づいて、飛びかかって、そのしっぽをひっつかんでしもうたんや。いくら人を騙すのがうまいきつねでも、ひとたまりもなく、そこにあった杉の木にしばり上げられてしもうたんやと。だけどきつねが、「もう悪い事はせん、人間の前には姿も見せん、かんにんしてくれ。」と、泣いてたのむさかいに、彦太郎は、かわいそうになってはなしてやったんや。それから、ぎょんどさんでは、きつねに騙されたという話は聞かんようになった。
丁坂(ようろざか)
昔、飯降山(いふりやま)に、三人の若い坊さんが修行をしていたんやと。
その坊さんらは、食糧を持って山にこもったんやけど、何しろ若い坊さんやから、それらをみな食べつくしてしまったんやと。
それで、何にも食べる物はなくなってしまうし、山を途中で降りると、和尚さんにしかられるから山を降りて食物を持ってくることも出来なんだんや。それで毎日、木の実や木の根などで飢えをしのいで修行をしていたんやと。
それを上の方から、そう、天の上から神さまが見ていたんじゃと。
「ほう若い坊主たち、食糧がなくなったというのに、けっこうしんぼうしているわ。けど腹がへっていては、満足に修行も出来まい。わしが、毎日三人に一食ずつ飯をあたえてやるとしよう。」
と、いって、神さまが、毎日一食ずつ飯を降らせたんやと。坊さんらはうれしくて、どもならなんだやと。何せ何もなかったさかいに。
若い坊さんのことや、一日に一食ではたらなくなったんやけど、天から飯をもらえるものだから、もう木の実や木の根まで取って食べようとは、しなかったんやと。
天から、飯が降ってくるまでは、木の実や木の根までも食べて修行をし続けようとした心が、何もせんでも食物がもらえるという、俗世界の煩悩に打ちまけてしもうたんや。ある日、一人の坊さんが、
「これいま、天から三食の飯が降ってくるのだから、もし一人居なくなれば、三食の飯を二人で分ければ、もっと腹がふくれるやろ。」
と、思い、一人の坊さんが用たしに出てるすきに、残った坊さんに話をして戻ってきた坊さんを殺してしまったんやと。ほいで、次の日に天から降って来るのを待っていたら、天の神さんなにをまちがえたのか、二食しか降らさなんだんやと。
次の日も次の日も、二食しか降って来んもんやさかいに、
「これはおかしい、この二食はわしの物にちがいない。どうもあいつが邪魔になるわい。」と思い、もう一人の坊さんのすきを見て、殺してしまったんやと。そして、次の日になって飯を待っていたら、一食しか降って来なんだんやと。そして次の日も次の日も、一食しか降って来んもんやさかいに、坊さんは、修行の事なんか忘れてしまい、山を逃げ出したんやと。ほいで山道を、腹がへっているものだから、よろよろと下りていったさかいに、それから、その道を丁坂と呼ぶようになったんやと。その山はもちろん飯降山と呼ぶようになったんやと。
おだけさんのせいくらべ
昔、神当部に、大変まつり好きのおじいさんがおったんじゃ。そのおじいさんは、秋まつりの時期ともなると上味見はもちろんのこと、河原や折立はおろか、池田までも出かけて行くほどで、この秋も、おじいさんは、池田の稲荷神社のまつりに、行ったんじゃと。そこで、酒を飲んだり、歌ったり、踊ったりしていたんじゃ。世の中には、似た者同志がおるもんで、神当部のおじいさんみたいな、まつり好きのおじいさんがおったんじゃ。そのおじいさんは、武生の新庄から、わざ、わざ、やって来たんじゃと。
おじいさんたちは、その場で始めて会ったけど、それは、似た者同志、もう昔からの親しい友達が、何年ぶりかに会ったみたいに、話がおうたんじゃ。
「のお、神当部のおじいさんや、神当部には嫁に出すような、ええ娘はえんかのお、うらんとこの孫に嫁をもろうてやりとうてのお。」 「ほやのう、うらんとこにはえんけど、ほねおってみよかの。」 「たのむわの、おじいさん、まあ一杯、飲んどくれの。」 と、言うような話になり、今年の稲はどうかとか、山の木はどうかとか、話はつきなんだんや。
二人は仲よう、飲んだり食べたり歌とうたり踊ったりしていたんや。ところが、しばらくして、酒があんまり入ったのか、どうかはわからんけど、だんだん自分の自慢話をするように、なったんじゃ。自分の家は、昔からの名家だとか、財産がいっぱいあるとか、お互いが競争しているみたいに、あることないこと、言うていたんじゃ。そうしているうちに山の話が、出て来て
「のお、神当部のおじいさんや、あんたとこには、なんでもあるやろうけど、山だけはうらんとこには、勝てんやろのお。」
「なに言うているんやの、うらんとこには、おだけ山て言うてそれは、高い山が、あるんやだ。」
「それは、ほんとけのお、うらんとこにも、おだけ山て言うて高いばかりか、美しい山があるんや、武生一やって、言われているんやだ。」
「なんや、武生一やったら、うらんとこの方が、高いわのお、なんせ、越前一やさかいのお。」
「おじいさん、あほなこと言わんといておぐれの、新庄の方が高いに決まっているわの。」
いくら、話していても、お互いに合いゆずらんもんで、どちらともなく、
「そんね言うなら、おじいさん、一辺、背くらべをしてみよかの。」
「ほう、それはええ、まあ、そんなことせんかて、わかっているやけど。」
「それは、こっちの言うことやわの。」 と、言うてお互いに、それぞれの村に、帰って、どうして計ったらいいかと、考えたんじゃと。
そして、いろいろ考えたあげく、両方の山のてっぺんに、長い長いあゆみ板を乗せて、その上にまるい玉を、置くことにしたんじゃと。おじいさんは、何日も何日もかかり、長い長いあゆみ板を造り山にかけ、玉を置いたんじゃ。
始めは、真中に止ったまま、全然動かなかったんやけど、神当部の方から、新庄の方に向って、突然、強い風がふいて、玉は少しずつ新庄の方へ転り始めたんじゃ。それを見て、神当部のおじいさんは、喜こんだが、風がやんだので、玉が止ってしまったんじゃ。いや、止まるどころか、今度は反対に、神当部のおだけ山の方へ、転がり始めたんじゃと。そして、神当部に近ずくにつれて、だんだんいきおいがついて、そのまま玉は、山を転がり、落ちてしまったんもんで、新庄のおじいさんは喜こぶし、反対に、神当部のおじいさんは、くやしがって、そのまま、寝こんでしまったんじゃ。
あれだけまつり好きの、おじいさんが、神当部のまつりさえも、出て来ないようになったので、村人達も心配して、おじいさんの、様子を見に行ったんじゃと。そしたら、おじいさんは、 「くやしい、くやしい、あと少しで勝てたのに、ちきしょう!」 と、寝言を言いながら、寝こんでいたんじゃと。 そこで、村の人達は集まって、なんとかおじいさんを、喜こばせてあげよと思い、いろいろ考えたあげく、おだけ山に登るときには、石ころを、一つづつ持って行って、それを頂上に積み上げようと、決めたんじゃ。それから、村の人達は、山に登る時には、ふところに、一つづつ石を入れて持って上がり、それを、積み上げたため、今では新庄のおだけ山よりも、ずーとずっと、高くなったんじゃと。
そしたら、おじいさんの病気も、なおったんじゃ。
「うそやと思ったら、一辺おだけ山に登って見ないのお、いっぱい石が積み上げたるさかいにのお、それから、登る時には、石を持って登っとくれのお。」
カッパの川太郎
昔、中手のはんざの後ろの川は、深く、青くよどんでいたんじゃ。
その川には、イワナやウグイがいっぱい泳いでいたんじゃ。春にもなると、小鳥がさえずり、タンポポやスミレなどの花に、ちょうちょうが飛びかうようなのどかなところやったんじゃ。その川には、魚ばっかりでなく川太郎ちゅう河童が住んでいたんじゃ。
人間にたとえれば、十五・六才じゃった。川太郎は、なかなか人には顔を見せなんだので、うわさにもならなんだんじゃ。だから、どこから来て、いつから住んでいるのかは、わからなんだんじゃと。
そんなある日の事じゃった。
川で泳いでいた子供が、あばばになって、村の人が大騒ぎしているのを見た川太郎は、 「これは、おもしろい、うらも川の中で子供の泣き声をまねて、さわぐと、村のもんが助けに集まってくるかもしれんぞ。」
川太郎は、泣きまねをするのは、うす暗くなってから、する事に決めたんじゃ。そうすれば、人には河童か人間かの区別がつかんからじゃ。
なんせ、河童の大きさは人間の六、七才の子供ぐらいじゃったからじゃ。川の中から、子供の泣きさけぶ声が聞こえてくるもんじゃから、そばを通った村人が、大あわてでそこいらに、転がっていた木やらなわを、差しだしたんじゃ、ほいたら、川太郎は、まってましたとばかりに、それを引っぱるもんだから、村人は、たまらず ”ドボーン”!
なにしろ、川太郎の力といったら、大人三人かかっても、かなわんほどじゃった。村人は、これが、河童のしわざとは、思いもせんかったんじゃと。ある日のこと、その川の近くにげんごろうさんが馬をつれて草刈にやって来たんじゃと。げんごろうさんは、そばにあった杉の木に、馬をつないで、さっそく草刈を始めたんじゃと。馬はつながれているので、尻を川にむけてじっとしていたんじゃ。これを、川の中で見ていた川太郎は、よせばいいのに、いたづら心をおこし、馬のシッポをつかんで、川の中へひきずりこもうとしたんじゃと。しかし、いくら川太郎に力があるといっても、やはり馬には勝てなかったんじゃと。そしてまたたくまに、川太郎は、土手の上にひきずり上げられてしもうたんじゃと。川太郎もびっくりしたが、そばで、草刈をしていたげんごろうさんも腰ぬかすほど、びっくりしたんじゃ。
なにしろ、げんごろうさんは、河童が昔からいるとは、知っていたが見るのは初めてだし、一人じゃったので、もう草刈どころではない、げんごろうさんは、村へととんで帰り、今見たことを、一部始終村の人に話したんじゃと。村の人は、なかなか信じてくれなんだんじゃが、川に引きこまれた人が、何人もいることなどから、あれは、河童のしわざにちがいないと言うことになり 「それならば、一つ河童をこらしめてやろう。」 と、言うことになったんじゃと。
村人達は、手に手にカマやクマ手などを持って、河童をさがしに、行ったじゃと。そんなこととは知らず、川太郎は、あんまりにも陽気がええもんやで、土手の上で昼寝をしていたんじゃと。村人達は、そこを見つけ、そっと近づき、なわでくくって、杉の木にくくりつけたんじゃ。川太郎は泣いて、
「もう、悪いことはせんで、はなしてくれ。」と、たのんだが、村人達は、そのままにして帰ってしまったんじゃと。
この日は、ものすご暑っかったもんで、杉の木にくくられた、川太郎は、頭の皿の水が心配になり、必死になって助けを、求めたんじゃと。なにしろ、河童は皿の水がなくなると、死んでしまうからじゃ。しかし、村人達は、知らん顔をして、いたんじゃと。しばらくして、河童の声が聞こえなくなったもんで、見に行ったところ、河童は、死んでしもうたんじゃと。
村人達は、可哀想に思って、その場所に、お地蔵さんを建ててまつったんじゃと。
赤子かべと岩になった夫婦
河内の的坂の南の谷に、白谷という谷がある。その谷の真中に赤子かべという岩かべが一つある。 岩かべの上が平になっていて、そこに或日赤子が捨てられていたんじゃと。その赤子はひもじくて、「おぎゃあ、おぎゃあ」と一日中泣いていたんじゃと。そのとき、その赤子かべから、五、六百米下の藪かげで、若い夫婦が、山を下りかけたり、上ったりしていたんじゃと。
この夫婦は、あの寺の盆踊りの夜、仲がよくなって、親の許しも得ず夫婦になったんじゃと。そして赤ちゃんが生れた。可愛い赤ちゃんを二人は、だき上げて、ほほずりして、どうかして立派に育てたい二人はそう思ったそうな。どんなに苦るしくとも二人で仕事にはげめば、この子を育てられると決心したんじゃと。
じゃがの、村では仕事がなく、又ききん年がやって来たんじゃ。夫婦はもうどうしようもなく、赤ちゃんを捨てに来たのじゃそうな。それでも赤ちゃんの泣く声をきくと、その壁のそばをはなれられないで、山をのぼったり、おりたりしていたんじゃそうな。 夕暮れになって、泣く声がやんだ。「ねたのじゃろうか。」「さあ、いまのうちに村へ帰ろう。」二人はそういったが、やはり気になって仕方がない。そっとのぞいてこようと二人は、又、岩かべに上ってみたそうな。そると、もう赤ちゃんの姿は見えなかったんじゃと。
どうしたのだろう二人は大きなかべの廻りをさがしてあるいた。そるとかべの下に大きな穴があって、その中の奥の方から赤ちゃんの泣き声が、きこえたんじゃと。それは、あるかなきかの小さい声じゃったが、穴のずっと奥の方から風が吹き上ってくる音と共にきこえたんじゃと。穴は小さくとても大人では入られず、二人が穴の中に顔を入れて耳をすますと奥の方から川の水音がきこえたんじゃと。奥の方に川があるらしい。この川はどこえつづいているんじゃろうか。 二人は、狂ったように山をおりて、村の物知りぢいさんの所へかけこんだんじゃと。「あの白谷のかべの下の穴はどこへ通じているんじゃいの。」と、二人は泣きながらきいたらの、物知りぢいさんは、二つに折れたこしをのばして、「あの穴はのう、村の奥の大牧口の青淵の下じゃ、あの淵の下に穴がある。白谷の穴は、あの淵へ通じているんじゃ。」と、教えてくれたそうな。 二人は、そくざに、奥の青淵へ走った。青淵は、白谷から南へ山を二つ越した山の中のくぼ地の、大きな岩の重なった下に、青黒くよどんだ深い淵があった。二人はその岩を伝って淵岸に降りていったそうな。淵には、つたや、くずねふじが密生してすごいうずまきになって、よどんでいたそうな。 二人が、岩の下cをのぞくと白谷の方に大きな穴があって滝のように水が流れおちていて、奥の方からは、小さく、遠く、赤子の声がきこえたそうな。二人は狂喜して穴のかたわらに待っていたそうな。今に赤子が流れ出てくる。今に赤子が流れ出てくると、しかし、赤子はいくら待っても流れてこなかったそうな。 そして夫婦はそのまま、そこで、石になってしまったそうな。
今も青淵の上に、赤子をまつ夫婦の岩が、そこに立っているそうな。
奇岩
○ 河内の山には、十六むさしが書いてある岩がある。 この岩の上に、かやなどを干すと雨が降るという。
○ 夫婦岩という名の岩には、弁慶のわらじの跡がついている。
赤子岩
○ むかし、乞食が赤子を生んだ。しかし、食べていけないため岩の下へ埋めた。それ以来、その岩は赤んぼうのなき声がしていたという。
○ 女の人がふきを取りに行き、赤子を生んだ。それを岩のそばへ埋めたら、岩が赤子の頭のような形になった。 故に赤子岩という。